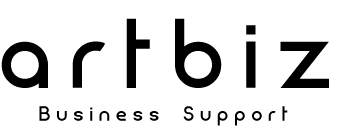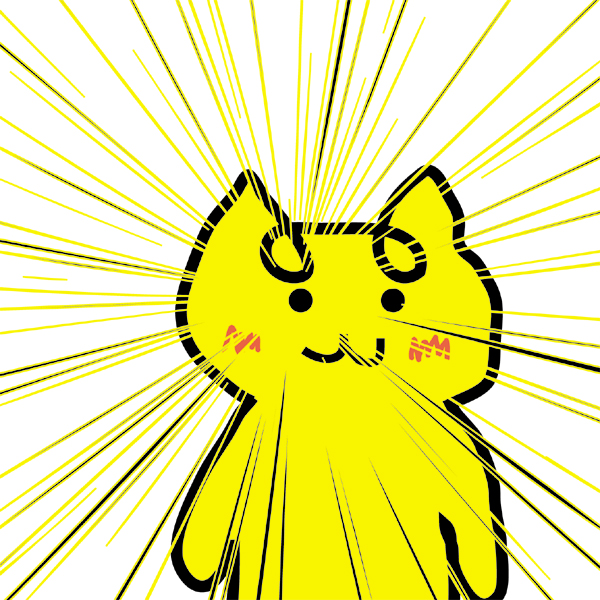「お金なし、知名度なし、人気生物なし 三重苦の弱小水族館に大行列ができるワケ~来場者12万人から40万人へV字回復」
ITmedia ビジネスオンライン 2018年06月08日
http://www.itmedia.co.jp/business/articles/1806/08/news041.html
「予算がない、スタッフが少ない、そもそも客が来ない」という、うまくいっていないお店と全く共通する悩みを抱えた地方の水族館がどうやって成功の道筋を描いたのか。とても参考になる記事です。
この記事の中で注目すべきポイントを抜粋してみました。
—
◎「魚マニアの自分たちがやりたいことではなく、普通のお客さんが求めているものを作っていく」ことの重要性
◎客の意見を取り入れるには、館内の客を「観察」するしかない。現在、竹島水族館のスタッフは、自分が担当する水槽の近くにじっと立っていることがある。「何人が立ち止まっていて、何分間ぐらい見てくれたか。一緒に来た人とどんな話をしていたか」を調べているのだ。
◎「200人のお客さんにアンケートを取ったこともあります。その結果、魚の研究目的の人は1人しかいませんでした。フグの調理師免許を取るためにフグの勉強をしに来たそうです。他の人たちはなんとなく遊びに来ているんです。ただし、うちで楽しく過ごした後に魚をもっと知りたくなり、ネットで詳しく調べたという声は聞きます」
◎魚を専門的に学ぶのではなく、魚に興味を持つきっかけを提供できる水族館を作ればきっとうまくいく。深海魚が多いことぐらいしか特色のない竹島水族館は、「お客さんに楽しんでもらう」ことに向かってスタッフ全員が切磋琢磨するしか活路はないのだ。
◎個人の責任を明確にし、創意工夫を引き出すために、人事制度を立候補式の「担当制」である「単独性多担当持ち」に変えた。上司が指示した水槽をチームで管理するのではなく、自分がやりたい水槽を立候補制で申し出て、飼育から展示までを基本的には1人で担うのだ。
◎「展示が面白くなくてお客さんから素通りされるようなことが続くと、他の人に担当を替えられてしまいます」。自分が担当している水槽の管理を効率的にこなし、人気のある展示を作ることができれば、好きな生き物を他の人から「奪いに行く」ことも可能なのだ。この制度のおかげでほどよい緊張感が生まれ、ダラダラと働くスタッフはいなくなった。
◎予算がない、スタッフが少ない、そもそも客が来ない。かつての竹島水族館のような状況にある会社は世の中に多い。言い訳のネタならば事欠かない。しかし、環境が悪ければ悪いほど、「お客さんが求めることをなりふり構わずにやってみよう」と開き直ることもできる。起死回生の改革案や本当に顧客に喜ばれるアイデアはそこから生まれるのだ。
—
この記事が教えてくれることは
◎自分(事業者側)がしたいことではなく、客が求めることを徹底して追求していくこと。
◎気軽に普通の人が楽しめる仕掛けをつくること
◎スタッフには一人ひとりに担当と責任を明確に割り振って完結させ、競争させること。
これら3点に尽きるでしょう。
事業をしていると、つい自分目線になってしまい、第三者の視点が自分のなかで薄くなってしまうのです。また、社内は社内で「指示を出す」側と「指示を受ける」側に二分されてしまう・・・。「大衆のウケ(ニーズ)」を意識するプレゼンテーションと、「責任を全うさせる」スタッフの役割分担。
学ぶべきポイントです。