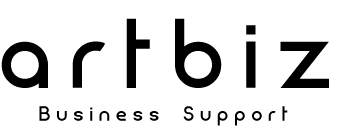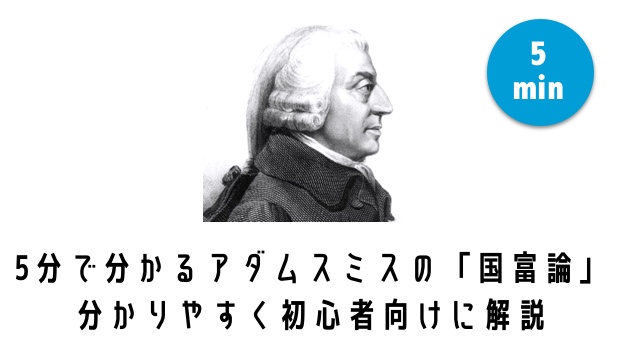椅子の世界にもアダム・スミスの分業論が導入され、工場では毎日、椅子の「脚」だけしか作らない職人がいるようになった。
彼らは自分の作った脚が他の職人の作った部品とピタリと合うように、会社の決めた部品規格や品質基準に組織ぐるみで従うことを求められた。人が機械のように働くことが重要になった。
そうなると個人はモノ作りの楽しさから遠ざかってしまう。また顧客の不満を自分の痛みとして感じ取る度合いも低くなる。
完成した椅子がいくらで売れるかよりも、自分は賃金さえもらえればいいという人が増える。
(中略)
産業革命以来、工場労働者に起きたこの現象と同じことが、二十世紀後半、日本企業のホワイトカラーに起きているのではないか。
本社の中で、本来なら経営の枢軸にいて「経営の面白さ」「経営の創意工夫」に生き甲斐を見いだすべき日本のエリートの多くが、分業の機能別組織に閉じこもり、椅子の脚だけ作っているパーツ職人になっているのではないか。
~P.154より引用~
『V字回復の経営』(三枝匡・著、日本経済新聞出版社)
分業することで生産性が高まるという、アダム・スミスの分業論。
しかし、「停滞は減衰のもと」で、
分業がいいのだ!と分業を専ら続けていくと、それが形骸化し、分業そのものが死んでいきます。
つまり、全体の中の自分の役割を見いだした上での分業であれば分業が機能するけれども、全体が見えなくなって分業を続けようとしても、今度はその分業の中だけで「自分は給料をもらっておこう」というだけの狭い価値観を助長させることになってしまう、という訳です。
ということで、分業の次の時代に来るものは、三枝匡さんが仰るところの「スモール・イズ・ビューティフル」で特定の商品に特化した小さなビジネスユニットを組んで、全メンバーが顧客・商品開発・生産・販売・利益を意識しながら全体を俯瞰しつつ自分の役割を全うしていこう、という流れになります。
このように、唯一の正解があるのではなく、
正しい理論の間を、粒子が振動するように行ったり来たりしながら、変化を恐れず、常に動きがあるということが大切なのですね。
「流れのない池の水は腐る」に通じます。